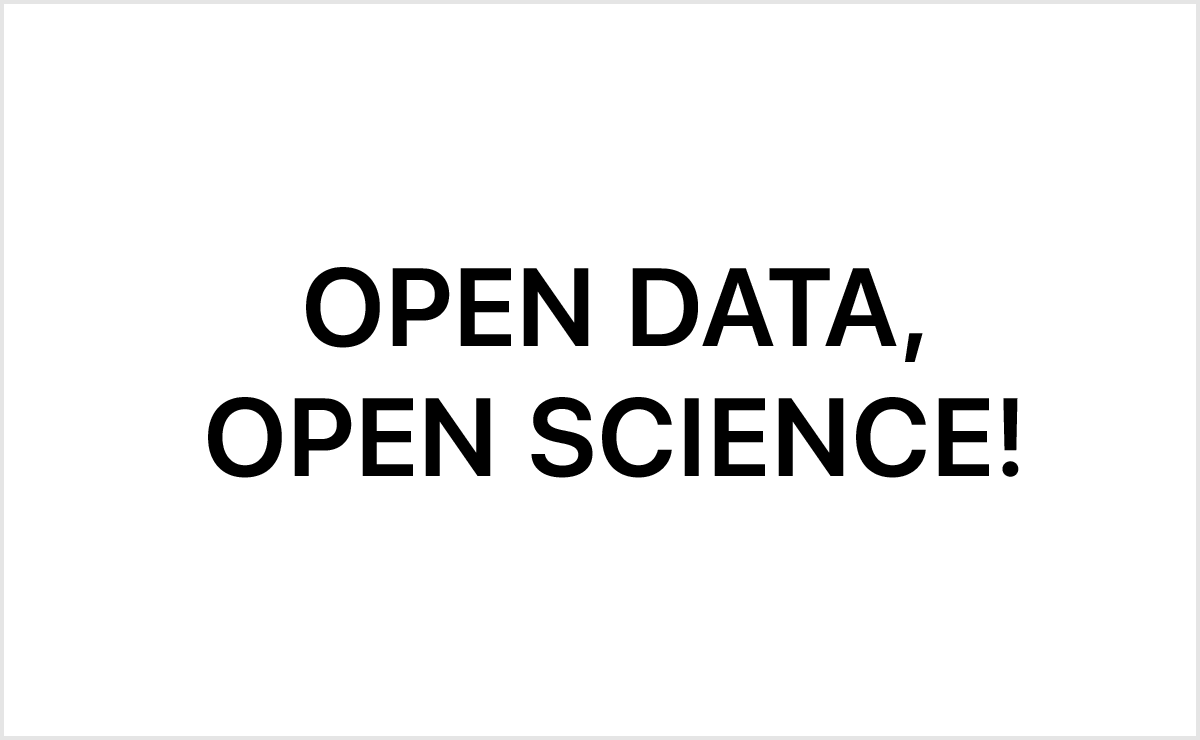FY2026 1Q Financial Results
2026年4月期
第1四半期決算
※ご使用の機器やネットワーク環境によっては、ご視聴いただけない場合がございます。また、当ウェブサイトやライブ中継をご視聴いただくための通信料につきましては、各個人のご負担となります。
決算説明動画の目次
-
資料の前提に関するご案内 1:26
-
2026年1Q 決算概要 2:54
-
2026年1Q 事業の状況 13:08
-
第2時中期経営計画の進捗と今後の方針 19:32
-
Q&A 21:34
決算資料
決算説明会のQ&A
経営・財務関連
スマレジ保守サービス料の計上方法変更が、1Qの売上高内訳に与えた影響額について、もし変更がなかった場合の売上高やARRの目安もお聞かせください。
本件は、会計方針の変更による内訳科目の振替であり、売上高の総額には影響はありません。1Qの実績では、この変更により「月額利用料」が68百万円増加し、同額が「機器販売」から減少しています。この結果、ARRは約2.7億円押し上げられる効果があり、仮に変更がなかった場合の通期ARRは91.6億円となります。
1Qに見られた売上総利益率の改善について、その持続可能性と具体的な要因、今後の見通しをお聞かせください。
1Qの売上総利益率の改善は、主に2つの要因によるものです。
- 高利益率のサブスクリプション比率向上といった売上ミックスが改善したこと
- 前期4Qに発生した一時的な費用が解消されたこと
これらを踏まえ、当面は現在の利益率水準を維持できるものと考えております。
2031年4月期の事業段階(ARR300億円想定)におけるOPM(営業利益率)の目安を教えてください。
第3次中期経営計画(FY2027〜FY2029)では、営業利益率20%前後を目標としています。2031年の最終ターゲット時点における具体的な目標は未定ですが、現時点でこの中期経営計画の目標水準と大きく乖離しない水準を維持していくイメージを持っています。
新中計は何月に発表予定でしょうか?
3Q決算発表のタイミング(2026年3月中旬)を目処に準備しています。従来通り、来期の見通しが出揃うタイミングで、より精度の高い計画を説明するのが適切だと考えています。
※現時点の見込みであり、確定ではありません。
製品・サービス関連
スマートPOSレジ市場の成長ポテンシャルと競合環境における自社優位性の確立方法、今後の成長シナリオは?
当社の強みは、POSを軸に決済や勤怠管理など周辺領域まで店舗運営を一気通貫で支援できる点にあります。さらに、アプリマーケットによる柔軟な機能拡張や、APIを通じた外部SaaSとの連携により、多様な業種・業態のニーズに対応できるエコシステムを構築していることが競争優位性の源泉です。
今後は、小規模店舗から大規模チェーンまでの導入実績を活かして顧客基盤を拡大するとともに、子会社との連携により小売・アパレル領域でのソリューションを強化し、持続的な成長を目指します
長期的なクロスセル比率の目標水準と、その達成に向けた戦略をお聞かせください。
方向性として、決済サービスはPOSとの親和性が高く、セットでの導入が主流のためクロスセル比率は高水準です。一方、HRサービスはプロダクトの性質上導入ハードルが高いため、現在の比率は決済事業より低い水準にとどまっています。
決済領域の競争環境について、足元で変化はありますか?
直近の競争環境に大きな変化はありません。決済端末の単体販売市場は競争が激しい一方、当社はPOSとのクロスセルを主軸としています。POSを起点とした包括的な提案により、決済領域においても競争優位性を確立しています。
決済事業のシェア獲得計画や、決算説明資料でのKPI開示の拡充予定はありますか?
決済事業の市場シェアや取扱高の具体的な目標値は、競争戦略上の観点から開示を控えております。しかし、同事業は大きな成長を見込む注力分野であり、今後も積極的に拡大していく方針です。開示KPIの拡充については、今後の事業フェーズに応じて前向きに検討してまいります。
営業・マーケティング関連
S&M比率は大きい一方でARRは良好。投資判断の参考として、現状または見込みのLTV/CACとNet Revenue Retentionを教えて下さい。
当社は先行投資として期初から積極的にマーケティング費用を投じております。費用対効果はユニットエコノミクス(LTV/CAC)で管理しており、前期末時点のLTV/CACは4.60(認知広告除く)、3.55(認知広告を含む)です。
Net Revenue Retention(NRR)は非開示ですが、参考指標として、決算説明資料p.20に掲載の「サービス利用開始四半期別MRRの推移」をご参照ください。既存顧客のMRRが維持されていることをご確認いただけます。
B2B事業におけるブランド認知度向上の効果測定方法と、今後のマーケティング費用のロードマップや重点施策についてお聞かせください。
当社はB2Bモデルとして、ペルソナやターゲットを明確に絞り込み施策を展開しています。効果・分析は、エリア別に四半期毎に実施する認知度調査やCTR(クリック率)やCVR(コンバージョン率)等のKPI比較で測定しています。
今後はWebでのリード獲得を主軸としつつ、代理店連携や中大企業向けも拡大していく方針です。すべての施策において、経路別のユニットエコノミクスを算出し、費用対効果を最重視した投資判断を徹底しています。
1Q広告宣伝費増加はテレ東の番組スポンサーの影響ですか?
番組スポンサーも要因の1つです。それに加えてテレビ局側の環境変化により出稿枠が変動した時期でもあり、当社としてもTVCMの投入を強化しました。結果として、「ブランド認知度向上」と、事業成長を加速させる「リード獲得」という、2つの目的の施策を同時に強化したことで、広告宣伝費全体が増加しています。
今後も積極的なマーケティング投資を継続されるとのことだが、1Q比較で進捗ボリュームの見通しを教えて下さい。
具体的な数値計画は非開示ですが、2Qもテレビでのスポンサー出稿等を継続しているため、1Qに続き高水準となる見込みです。今期の傾向としては、上半期は重く、下半期は例年並みとなる見込みです。